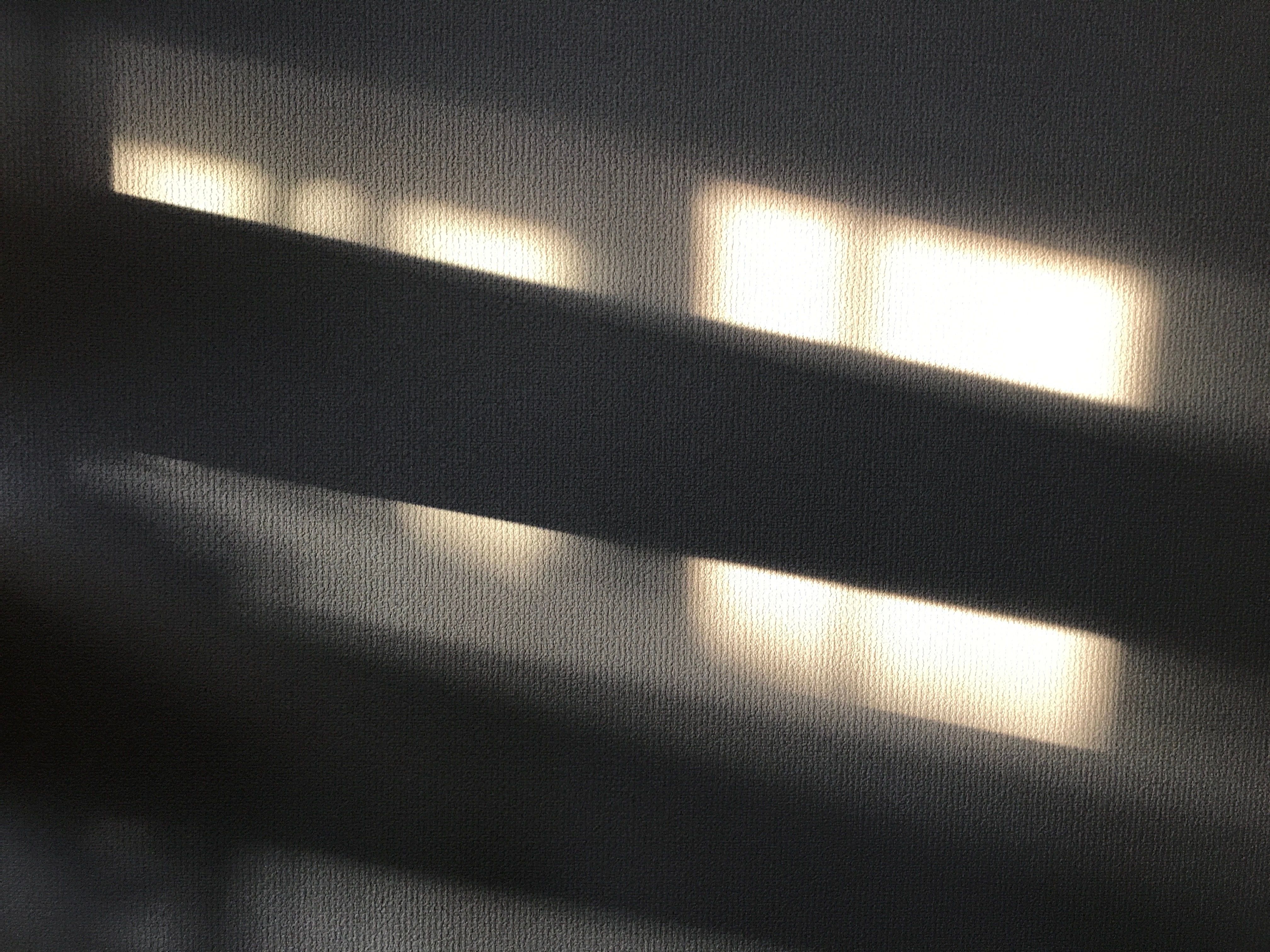『だから僕たちは、組織を変えていける』を読んだ。
自分のチームのマネージャーがもうすぐ育休に入る。育休中のマネージャー代理をさせてもらうことになったので、これをきっかけに組織開発について勉強しようとこの本を読んでみた。
どんな本か
これからの時代で目指したい組織として、学習する組織 / 共感する組織 / 自走する組織が挙げられていた。なぜそういった組織が良いと考えられるか、そういった組織にするにはどうしたらいいかが、いくつかの観点から書かれていた。
感想/メモ
シェアドリーダーシップ
「学習する組織」ではシェアドリーダーシップが有効。シェアドリーダーシップとは自然発生的なリーダーが想定され、時々に応じて最適なメンバーがリードするもの。
異なる職能を持つメンバー(e.g. PdM, BE, FE, QA, CS, Des, …)が集まるような事業部制組織ではシェアドリーダーシップのイメージはしやすい。自分が所属している職能別組織(BEチーム)でのシェアドリーダーシップはどういう形になるんだろうと考えてみた。
職能別組織で実践するには小さい分野から少しずつリードできる範囲を大きくしていくしかないんだろうなと思った。ビルド周りに詳しい人、DBに詳しい人、設計が上手な人等が別々にいれば、時々に応じてそれぞれがリードをすれば良さそうだが、ある人が大体において一番詳しいみたいなことも少なくなさそう。そういった場合は小さい単位(e.g. あるAPI)で自信を持てるような経験をして、少しずつ自信を持てる範囲を増やしていくといったことを続けることで、シェアドリーダーシップが発揮できる組織になっていくのかなと考えた。
5つのチーム成功因子
心理的安全性で有名なプロジェクト・アリストテレスでは、他にもチームの生産性を高める因子を挙げている。(心理的安全性以外の4つは知らなかった…)
- 心理的安全性
- 相互信頼
- 構造と明確さ
- 仕事の意味
- インパクト
それぞれでマネージャーとしてできることを考えてみた。
仕事の意味/インパクトについては、内発動機づけを促す、チームで大事にする価値を議論する/定める、Whyなどより上位の概念を伝えるなどだと理解した。相互信頼/構造と明確さについては、各メンバーがどんなものへ好奇心を持つのか理解する、丁度いい大きさの裁量を与える、コンフォートゾーンを抜け出す環境を提供するなどがあると理解した。
心理的安全性を含めて全ての因子を高めるためには、マネージャー自身の実践が大事だとも理解した。まず小さなことをやってみる、実践しようとする姿を示す、といった行動の積み重ねがチームを少しずつ変えていくんだなと感じた。